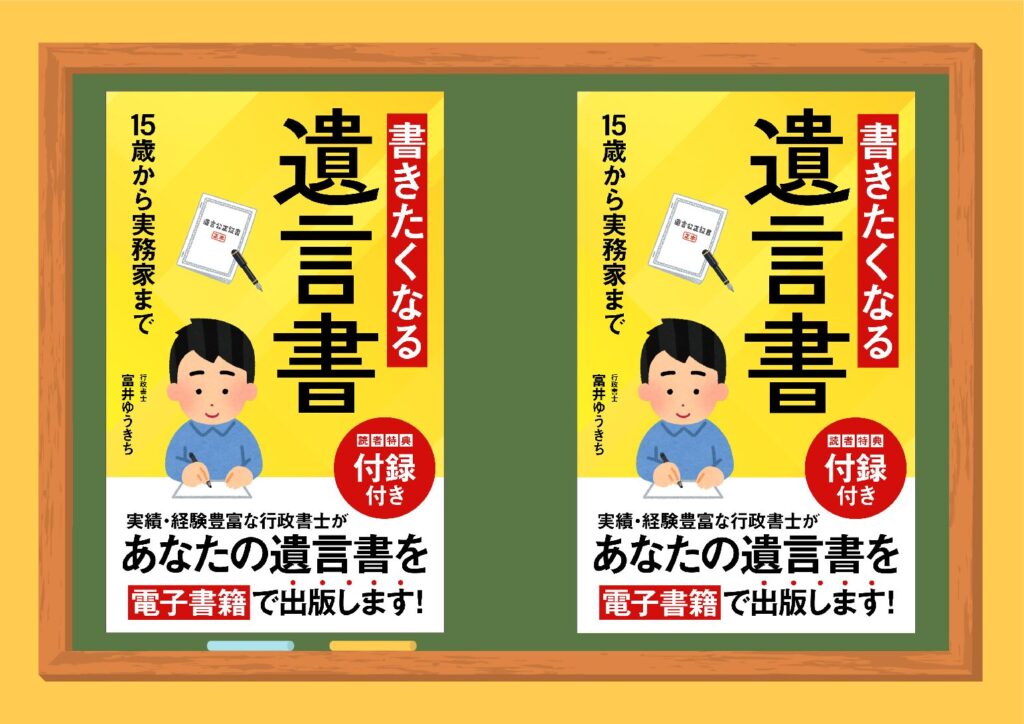① 子供のいない夫婦の場合
結婚しているが、子供がいない場合は、年齢に関係ありません。若い夫婦の場合は、相続人が親、義両親、兄弟、義兄弟になります。相続人の配偶者が、これらの人々を相続手続きを進めなければなりません。残された配偶者には、相当な負担となるのが、明らかです。
高齢の夫婦の場合は、相続人が兄弟になります。その兄弟も、高齢に違いありません。遺族が、高齢の配偶者ならば、施設に入所してたり、認知症になっていたりする兄弟と相続手続きを進めなければなりません。残された配偶者には、相当な負担となるのが明らかです。
② 離婚した前妻(夫)に、子供がいる場合
離婚しても、その子供は相続人です。どこで、どうしているのか?連絡先も分らない、場合も多いです。
残された配偶者、または、子供がその家庭に連絡して、相続手続きを進めなければなりません。残された遺族には、精神的に相当な負担となるのが明らかです。
③ 息子の妻や、孫に遺産相続させたい場合
自分が亡くなったら、残された配偶者の世話をしてくれるのが、息子の妻や孫です。当然、心配をなくするために遺産相続させたいことでしょう。
しかし、息子の妻は、相続人ではありません。1円も、相続できません。これでは、残された配偶者が心配です。その心配をなくするために、遺言しておくことが必要です。
④ 相続人以外の甥や姪に相続させたい場合
甥や姪と、縁が深い家庭も多いです。自分の家族と縁が薄くて、長年同居してお互い世話している。逆に、甥や姪が親族と縁が薄く同居している。田舎の土地、お墓を守ってくれている。
などの事情があって、相続人ではない人に相続させるには、遺言書が必要になります。相続人ではないので、遺言書にハッキリ書いておかなければなりません。
⑤ 家族が仲が悪い。揉めて、悪くなった場合
ハッキリ言って、相続人でない人が口を出してきます。典型的なのが、息子の嫁です。義実家の関係者や、親類などもです。だれも相続争いの、種を蒔きたい人はいないでしょう。遺言書があれば、遺言書に書いてあれば争いはなくせます。今は仲良くても、安心できません。
社会経済状況や健康問題で、将来まで保証できるものではありません。残された配偶者は、身につまされる思いになります。そのためにも、遺言書が必要なのです。
まずは、エンディングノートなどで練習してみることをお勧めします。
分らないことは、お気がるにご相談ください。
遺言書のことなら
街の法律家「 行政書士富井ゆうきち事務所 」まで、お問い合わせください

-640x1024.jpg)